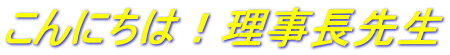 |
| 学校法人聖公会盛岡こひつじ学園理事長赤坂徹先生のページです! |
| ≪2021年12・2022年1月 合併号へ≫ |
|
参照:幼稚園保健2014、小児科臨床、67巻増刊号、2014
[言語]・会話が流暢になる。
・2語文を話し、助詞を適切に使う。
・好きな食べ物・嫌いな食べ物、幼稚園のクラスの名前、担任の先生の名前、仲良しの友達の名前を言える。
・しりとりをする。
[粗大運動]・片足立ち10秒以上
・片足ケンケン8~12回
・スキップやでんぐり返しをする。
・ブランコを立ってこぐ。
・ジャングルジムなどの高い所に登る。
[微細運動]・幼稚園の年少児から丸、年中児から四角、年長児から三角を真似して描く。
・人物画で目、口、鼻、耳、身体、手、足を描く。
・身体の各部の左右がだいたいわかる。
[社会性] ・排便が自立する。
・排尿のコントロールは夜間については完成していないので、夜尿があっても生理的現象と考えてよい。
・衣服の着脱が自分でできる。
・食事は箸を使う。
・食事の後片付けの手伝いなどをする。
2.発達障害とは何でしょうか
子どもの成長には発育(身長や体重の増加)と発達(身体の機能の進歩)のバランスが重要です。発達障害(しょうがい)は病気ではないのですが、対応を誤ると障害の程度が大きくなり治療が必要になることもあります。
1)発達障害かな?
子育てをしている時、次のようなことが気になりませんか。
参照:岩手県いわてこども発達支援サポートブック~こどもの成長によりそった子育て~
①
コミュニケーションや表現がうまくできない。
②
外出先や公園などで忙しく走り回る。
③
大人などの身振りのまねをしない。
④
大人が相手になっても喜ばない。
⑤
自分の好きなものがあると、他への切り替えができない。
⑥
“ごっこ”遊びができない。
⑦
身の回りのこと(着脱、排泄、片付けなど)がなかなか身につかない。
⑧
特定の物に執着する。
⑨
物音、振動、光なのに敏感(感覚過敏)で必要以上に怖がる。
2)発達障害が心配になったら
一人で悩まないで、幼稚園の職員や相談機関に相談してみましょう。思い込みで心配過剰にならないように、子どもの気持ちに寄り添って対応しましょう。⇒は対応例です。
①
特定のものに興味が強い場合⇒子どもの安心感を尊重しながら、ゆっくりと関心をひろげよう。
②
いつもと違うことに戸惑う場合⇒予定の変更は事前に繰り返し伝えておこう。
③
活動の切り替えに苦手な場合⇒活動を分かりやすく、絵を使って伝えよう。
④
生活の習慣づけが苦手な場合⇒声かけでは記憶に残らないので、習慣づけしたい事柄を絵に書いてカードにして渡す。できたらたくさん褒めよう。
⑤
落ち着いていることができない場合⇒静かで落ち着ける環境に移動する。落ち着いて出来るようになったら褒め、出来なくても咎めない。少しずつ成功体験を増やそう。
⑥好きなものの前ではルールを忘れてしまう場合⇒根気よくルールを身につけさせよう。守れたら褒めよう。
3)発達障害への対応
学校 ①保護者への連絡、持参する物などはメモにして渡し、できたら褒める。
②
パニックな状態になったら静かな部屋に移し、落ち着いたら教室に戻らせる。
③
運動会でスタートのピストルを笛に変える。バックグラウンド・ミュージックの音量を控える。
医療機関 ①発達障害の児童・生徒の診療になれた小児科医を受診させる。
②暗室で抑制されるレントゲン撮影では保護者から声をかけてもらって落ち着かせる。
③疼痛を伴う採血や予防接種では事前の説明と保護者の立ちあいで対応する。 |