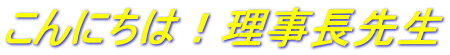 |
| 学校法人聖公会盛岡こひつじ学園理事長赤坂徹先生のページです! |
| ≪2022年6・7月 合併号へ≫ ≪2022年10・11月 合併号へ≫ |
|
1.災害は忘れた頃に、だから忘れずに備えましょう 暑い夏でしたが、地震、竜巻、ゲリラ豪雨、台風などの災害が幼稚園や外出先で起こった場合、どのように対応しらた良いか考えてみませんか。私達が経験した東日本大震災で学んだことを生かして対応しましょう。家族の災害対策日を大震災の3月11日か、救急の日の9月9日に決めて具体的に取り組んではみてはいかがでしょうか。 参考図書:衛藤隆 編著、最新Q&A 教師のための救急百科、第2版、大修館書店2018年4月20日発行 1)地震への対応 大きな揺れを感じたら、机の下にもぐったり、窓や棚から離れ、頭を覆って自分の身を守りましょう。緊急地震速報が出たらドアを開けて出口を確保してから、すみやかに安全な場所に移動しましょう。地震に伴う津波には波が届かないような高い場所や建物に移動しましょう。それに伴って電気、水道、都市ガス、自動車の燃料の供給が止まったり、火事が起こることがあります。 2)竜巻への対応 テントや物置などが飛ばされるほどの突風が吹く竜巻は発生場所や時刻を予測することが難しいようです。竜巻が近づいてきたら、室内に避難し1階のできるだけ窓のない部屋に移動しましょう。 3)ゲリラ豪雨・台風 夏に発生するゲリラ豪雨は園庭の浸水とともに、通園路の冠水や河川や側溝の増水などを引き起こします。増水した場所に近づかないようにし、安全な室内に避難します。早めに帰宅するか、園内に待機するなどの状況判断や気象状況を見ながら行います。 4)非常時に備えて ①非常食、非常用備品を確認しましょう。 非常食の賞味期限を確認し、家族で一緒に消費したら、次回の災害対策日まで補充しましょう。電池、カセットコンロの買い置きがありますか。自動車の燃料はいつも満タンにしておきましょう。 ②連絡方法を家族で確認しましょう。 学校、学童保育、幼稚園、保育園などのお子さんの居場所と連絡方法、避難場所を確認しましょう。帰宅した方が良いのか、施設内に留まって移動する時期を決めましょう。
2.発達障害とは何でしょうか 最近、発達障害という言葉があちこちで聞かれて、我が子のことかと心配している親御さんがいらっしゃるようです。子どもの成長には発育(身長や体重の増加)と発達(身体の機能の進歩)のバランスが重要です。発達障害は病気ではないのですが、対応を誤ると治療が必要になることもあるようです。 1)発達障害かな? 子育てをしている時、次のようなことが気になりませんか。 参照:岩手県いわてこども発達支援サポートブック~こどもの成長によりそった子育て~ ①
コミュニケーションや表現がうまくできない。 ②
外出先や公園などで忙しく走り回る。 ③
大人などの身振りのまねをしない。 ④
大人が相手になっても喜ばない。 ⑤
自分の好きなものがあると、他への切り替えができない。 ⑥
“ごっこ”遊びができない。 ⑦
身の回りのこと(着脱、排泄、片付けなど)がなかなか身につかない。 ⑧
特定の物に執着する。
2)発達障害が心配になったら 一人で悩まないで、幼稚園の職員や相談機関に相談してみましょう。思い込みで心配過剰にならないように、子どもの気持ちに寄り添って対応しましょう。 ①
特定のものに興味が強い場合 ⇒子どもの安心感を尊重しながら、ゆっくりと関心をひろげよう。 ②
いつもと違うことに戸惑う場合 ⇒予定の変更は事前に繰り返し伝えておこう。 ③
活動の切り替えに苦手な場合 ⇒活動を分かりやすく、絵を使って伝えよう。 ④
生活の習慣づけが苦手な場合 ⇒声かけで習慣づけしよう。できたらたくさん褒めよう。 ⑤
落ち着いていることができない場合 ⇒落ち着ける環境にし、少しずつ成功体験を増やそう。出来たら褒め、出来なくても咎めない。 ⑥
好きなものの前ではルールを忘れてしまう場合 ⇒根気よくルールを身につけさせよう。守れたら褒めよう。
|